最初に
2020年のテキストを取り出して再び勉強を始めてみた。
2020年のテキストを持っているということはその頃に何となくの勉強をしようとした挙句に、そのまま勉強を頓挫させたようだ。私自身にとって中小企業診断士の資格が何かに意味があるのかと問われれば十中八九何も意味がないのだが、老後などの時間を持て余しているような時には何か役に立つかもしれない程度の軽い動機になってしまっている。
そういう軽い動機だからこそ気合を入れて勉強ができないのであろうが、自分の子供が中学校受験に向けてSAPIXでひどい成績をとってくるたびに憤慨している自分をふと振り返ってみると、えらそうなことを子供に言っているにも関わらず、私自身も大して勉強できていないよなと自省するのであった。
ということで、子供に勉強しろ勉強しろと口を酸っぱくして言うからには、私自身もお手本となって日々何かしらの勉強をすべきだと、勝手に自分で判断したというわけだ。
これから中小企業診断士の勉強をしようとしている人達は間違っても古い中古本を買うのではなく、年度にあった最新の参考書を買うようにしてほしい。
企業活動とは
企業活動とは、企業が4つの市場との関わりを通して行う活動を指している。4つの市場とは:
- 金融市場:資金調達の場。直接金融/間接金融どちらもここに入る。
- 労働市場:人材の調達。正規・非正規社員採用。フリーランス・業務委託等。
- 原材料市場:製造する商品の原材料を調達。
- 製品市場:商品やサービスを提供する場所。
企業は、これら4つの市場に対して活動を継続、かかわりを常に持つ形でしつつ事業展開をする。これら4つの市場に対しる活動は、すなわち企業が行う外部環境に対しての活動ということになる。
企業活動の全体像
右は企業活動の全体像を表している。資金・原材料・労働力を市場から調達し、消費者等のニーズに合致した製品・サービスに変えて(付加価値を生み出して)提供する。

経営戦略の概念
経営戦略の概念はあらゆる本にあらゆる形で記載されているが中小企業診断士の試験に向けてはストレートにテキストからの文言で頭に叩き込んでおくのがよいのだろう。2020年度版のテキストでは下記の様に記載されている。
- 環境適応のパターン:企業がどのように外部環境とかかわっていくのか
- 将来志向的:現在のことだけでなく、会社の将来の方向性について
- 意思決定の指針:会社の人達が意思決定をする上での柱となるもの
2023年11月現在においては、円安、エネルギー価格上昇、物価上昇や長期金利上昇圧力等によって、好調な企業と苦しい企業の二極化が進んでいるようですが、どのような状況下においても企業は生き残りの道を模索し最良の戦略をとる必要があるだろう。
環境適応のパターンを今の状況に鑑みてみると、金融市場での資金調達はこれまでのコロナ禍の救済的な側面からは脱し、以前と同じような融資環境に戻っているようだ。他方で、海外金利の上昇との兼ね合いで、日本の長期金利も上昇圧力が常にあり金利動向には少々神経質になる必要はあるのかもしれない。
労働市場は人手不足が顕著ではあるものの、業界業種によって採用意欲に大きな開きがあるがそれは今に始まった話ではない。若い人材の採用意欲はどこの業界も高そうだが、求人への応募は実際には中高年の応募に偏ってしまう傾向も強く雇用のミスマッチは依然として解消されていない。中国経済の悪化に伴う中国国内の失業率の悪化からか中国人の日本企業への就職も増えているようだが、円安の影響からか海外人材からの人気は低そうではある。
原材料市場に関しては極めて先行き不透明かつ厳しそうだ。ロシアのウクライナ侵攻に伴う戦争、イスラエス・パレスチナの抗争と世界情勢に影を落としそうな出来事が立て続けに起こっているため、あらゆる原材料が高騰している。2023年11月現在、ガソリン小売価格はレギュラーでリットル165円前後だ。エネルギー価格の高騰で電気代も高騰しており、食料品等の日常生活に影響のある物価も軒並み高騰している今、それに伴う全業種がそれこそ的確な経営戦略を打ち出す必要があるのだろう。
製品市場も、原料高と消費者心理の冷え込みのダブルパンチで苦しいかじ取りを迫られているところだろう。
上記のような環境とどのようにかかわっていくか?を将来志向的に示し、企業内の人々の意思決定の指針としなければいけないわけだが、世界情勢やエネルギー情勢については先行きの予測を立てるのはほぼ不可能とすると将来志向的に戦略立てていくのは不確定要素が多く仮説の上に仮説を積み上げていく必要があるようだ。コロナ禍からその数を一気に増やしたリモートワーク主体の組織編制はこのような状況下における意思決定の難易度を高くしてしまう可能性もある。まさに意思決定の指針が必要な環境だといえるだろう。
定義上、経営戦略は3つの戦略で成り立っている。組織内においては自分自身の立場の変化と連動する形で見なければいけない領域が拡大していく為、そこまで意識せずとも戦略の階層を跨ぐ(あるいは間違える)ことはないだろう。特に事業戦略と機能戦略の兼ね合いは意識しないで間違えると(例:想定したターゲット顧客層と設定した価格帯にずれが発生している等)事業そのものが頓挫しかねない為注意が必要。
企業戦略(全社戦略)
複数の事業を行っていたり多地域展開をしている企業が、事業ドメインの決定や事業部間でのリソース配分など、企業/企業グループ全体にかかわる戦略策定をする場合に策定する。ある程度の規模の企業で事業部長級程度の立場にならない限りは「なんとなく知っている」程度の漠然としたイメージになるだろうか。組織に加わって間もない人でも明確に全社戦略が理解できている組織は強い組織が多い傾向がありそうだ。
事業戦略
一般論としては、事業部が異なればターゲット顧客層/販売する商品/担っている機能等が異なっているためそれぞれの事業部が相応の事業戦略を有している必要がある。規模が大きな会社であっても事業の柱が一個しかない場合には企業戦略=事業戦略にもなるので違いは明確に理解しておいた方がよい。
機能戦略
全社や事業部単位ではなく各機能の生産性を高めるための戦略は機能戦略と呼ばれる(人事戦略、営業戦略、マーケティング戦略など)。機能単位の事業部(営業部、人事部、経理部、システム部等)が決める目標等もあるが、基本的に機能戦略は全社戦略、または事業戦略が目指す地点に向けて生産性を最大化できるように設定される方が多い。
まとめてみた感想
やはり専門学校にお金を払って資格取得をする人がいるくらいなので簡単ではないだろう。試験の難易度もそうだが何よりも時間確保が一番難しそうである。何かしらの目的をもって資格取得が必須な人の場合は、年間計画を立てたり専門学校に通うなどして取得する方が学習ペースが維持できて良いかもしれない。
中小企業診断士の勉強はどこまでいってもアカデミア感が強い印象で、有資格者はどのようにそれらを実務に活かせるように強化しているのかには興味がある。財務諸表から判断しアドバイスしている限り税理士や会計士には勝てないだろうし、法律関連のアドバイスはそもそも顧問弁護士一択だ。にわかの知識で判断して事を進めるようなリスクを取る会社と中小企業診断士の接点があまりあるとは考えずらい。
組織構造そのものに問題を抱えているような会社は当然ありそうですが、そこは人事・組織コンサル等の方が相談相手の第一想起となってしまう。運営管理、経済・経済政策、経営情報システムあたりも別の第一想起専門家がいるので中小企業診断士の方が分が悪い。
「それらを広く理解しているのがポイントである」というのは詭弁で、どっちつかずの中途半端な人材になってしまうような気がする。勉強をすれば経営が上手くいったり、ビジネスで成功を約束されるわけはないし、他方で勉強も何もなしに行き当たりばったりで大成功を収めた人のような生存者バイアスがかかりまくりの人物にアドバイスをしてもらっても中々的を射たものがもらえるのかは疑わしい。
そう考えると王道は、既に専門性の高い資格やスキル、顧客網を持った人が顧客獲得の幅を広げたり、既存顧客へのアップセルをとる為の武器とするような形だろうか。その場合は自分自身が投下する時間(資格は個人に帰属するので)とそれに対するリターンとのバランスが重要になりそうだ。


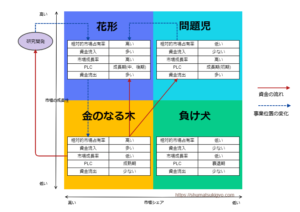

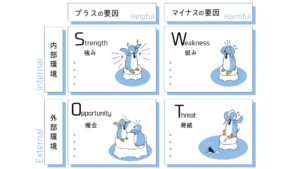

コメント